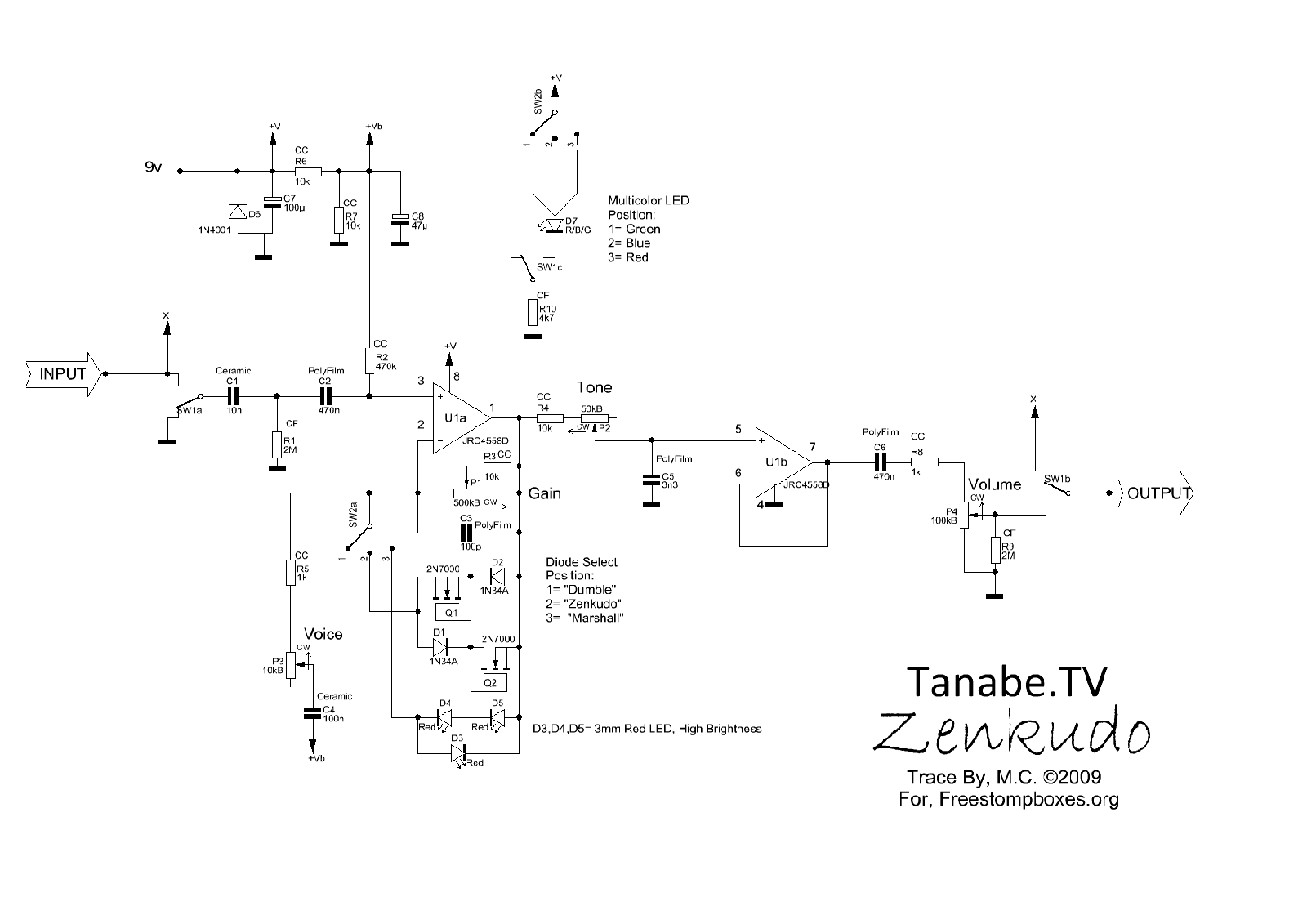昨日の記事の続き
Zendriveとは?
こちらの記事で書いている

(2万円以上、初期モデルは4万?)
トランスペアレント系OD
間違っているかもしれないので
信じないでね
Zendriveの回路はアンプライクだと言われ
「トランスペアレント系OD」という分類になった
その後、その回路を真似たエフェクターが
多く輩出された
クリッピングダイオードをチェンジできるZenkudoをはじめ
(3.2万)
Eternityや
(4万)
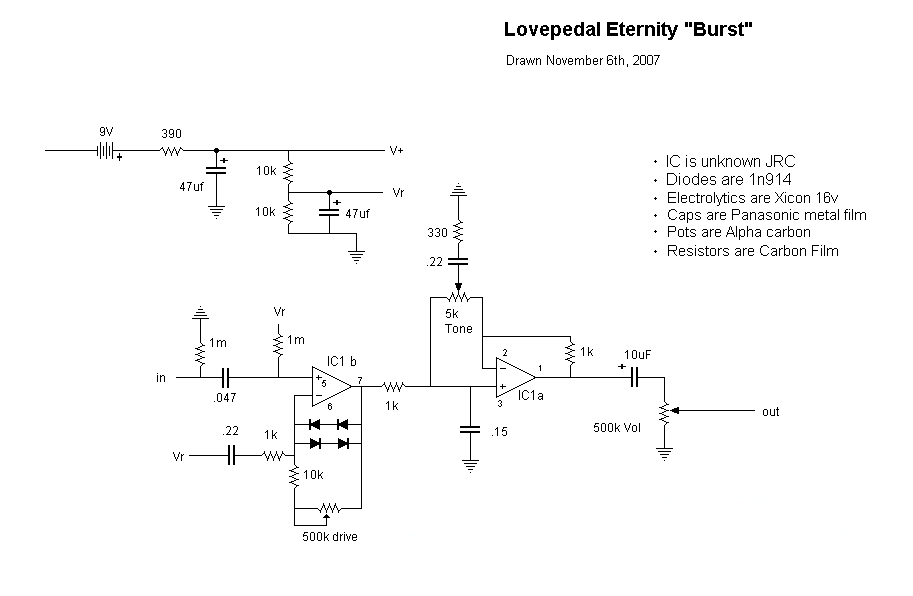
Timmy
(1.6万)
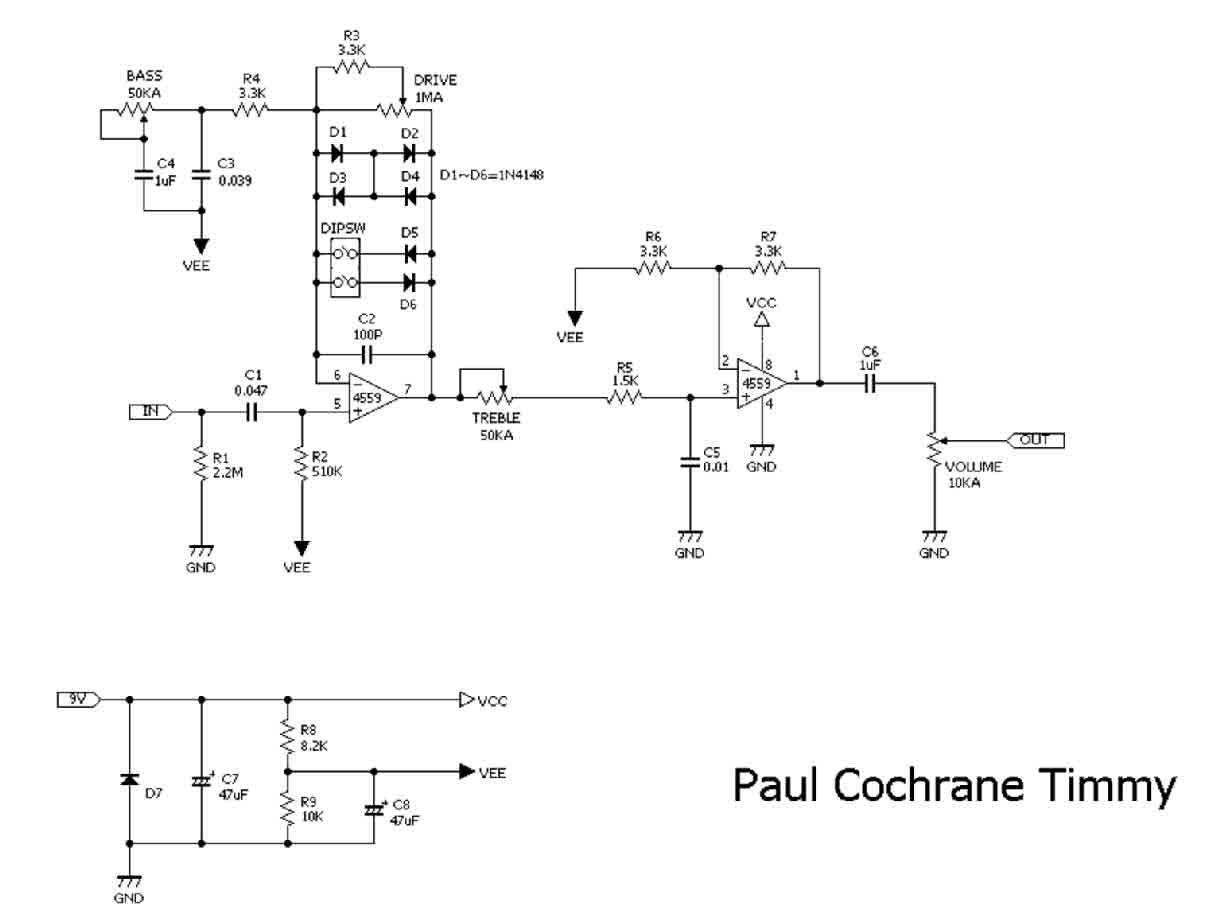
Vemuram Jan Rayといった
(4万)
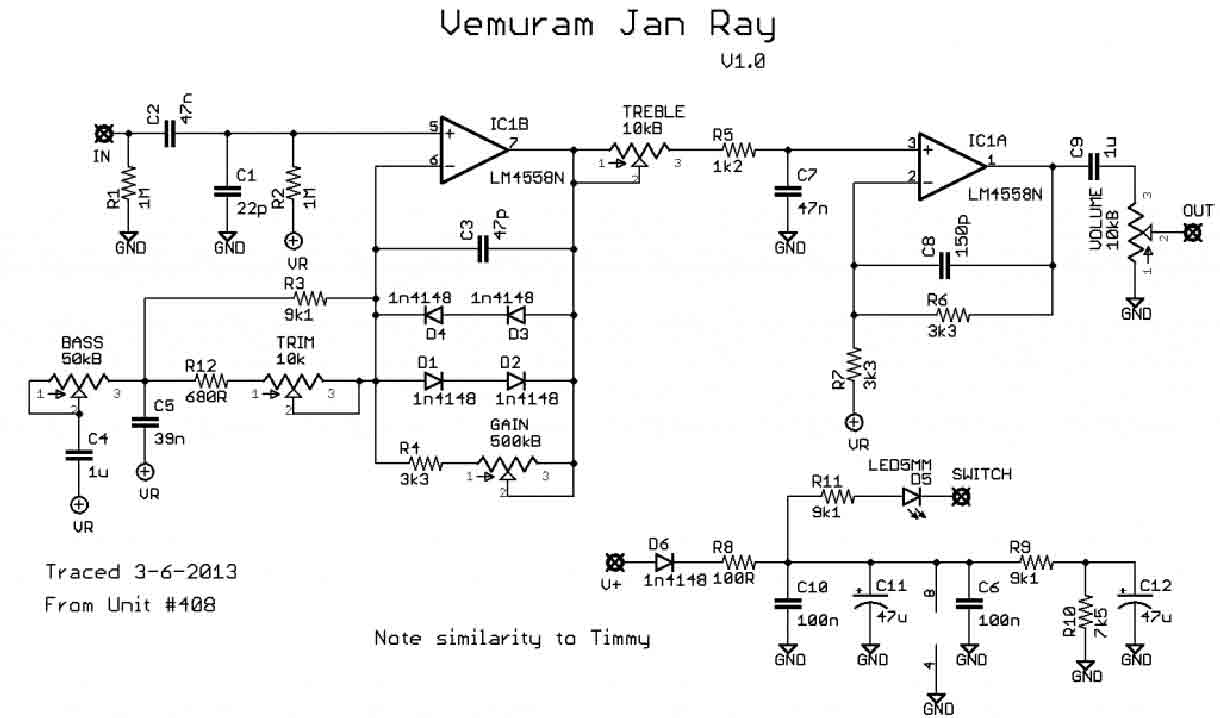

この回路図、
電源周りがちょっと間違ってないかな?
多くの定数違いのエフェクターが発売された
(簡単な回路だが、どれも高い)
改造の記録
私は
そんないろんなエフェクターの
いろんな定数を試して
分からなくなってしまったんだと思う
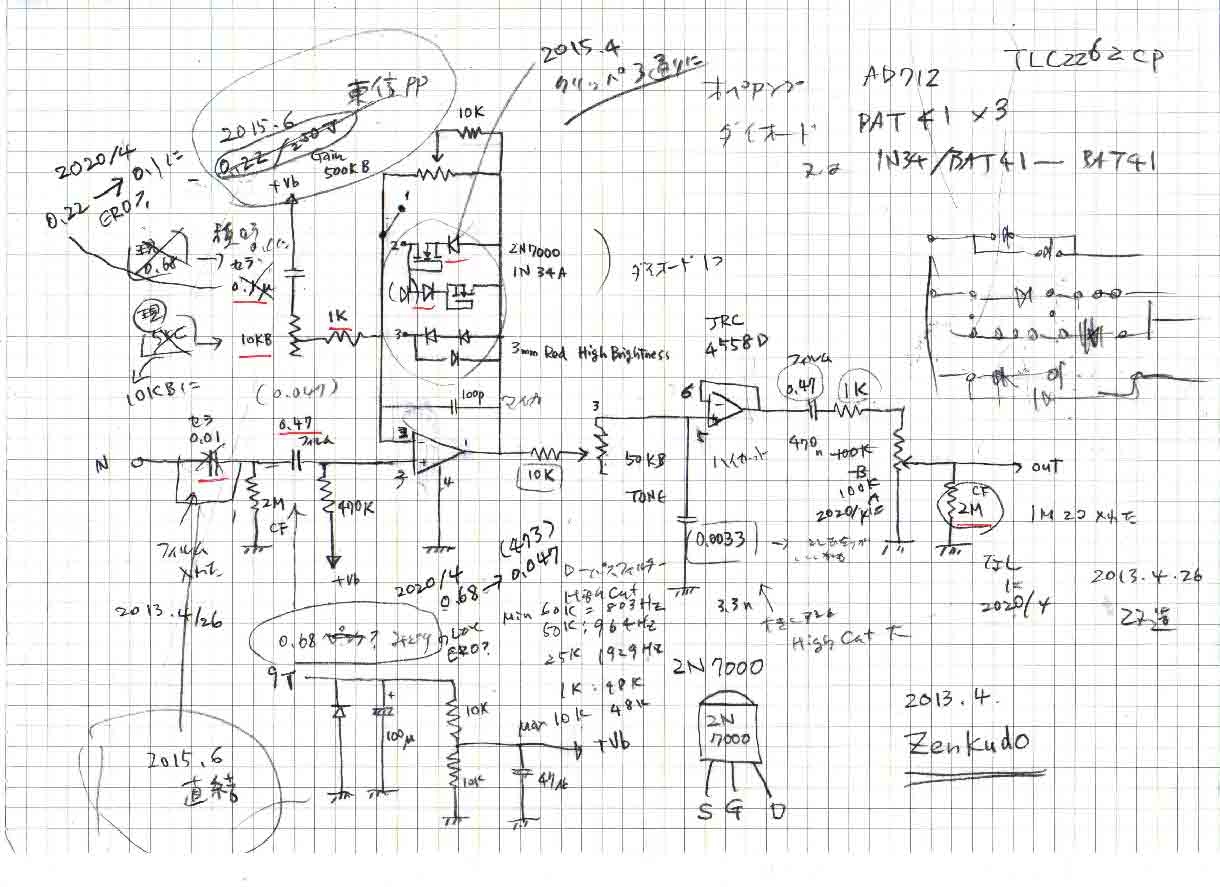
ソケット仕様
主要なコンデンサーがソケットで
取り替えられるようになっている
偉いぞ、昔の自分
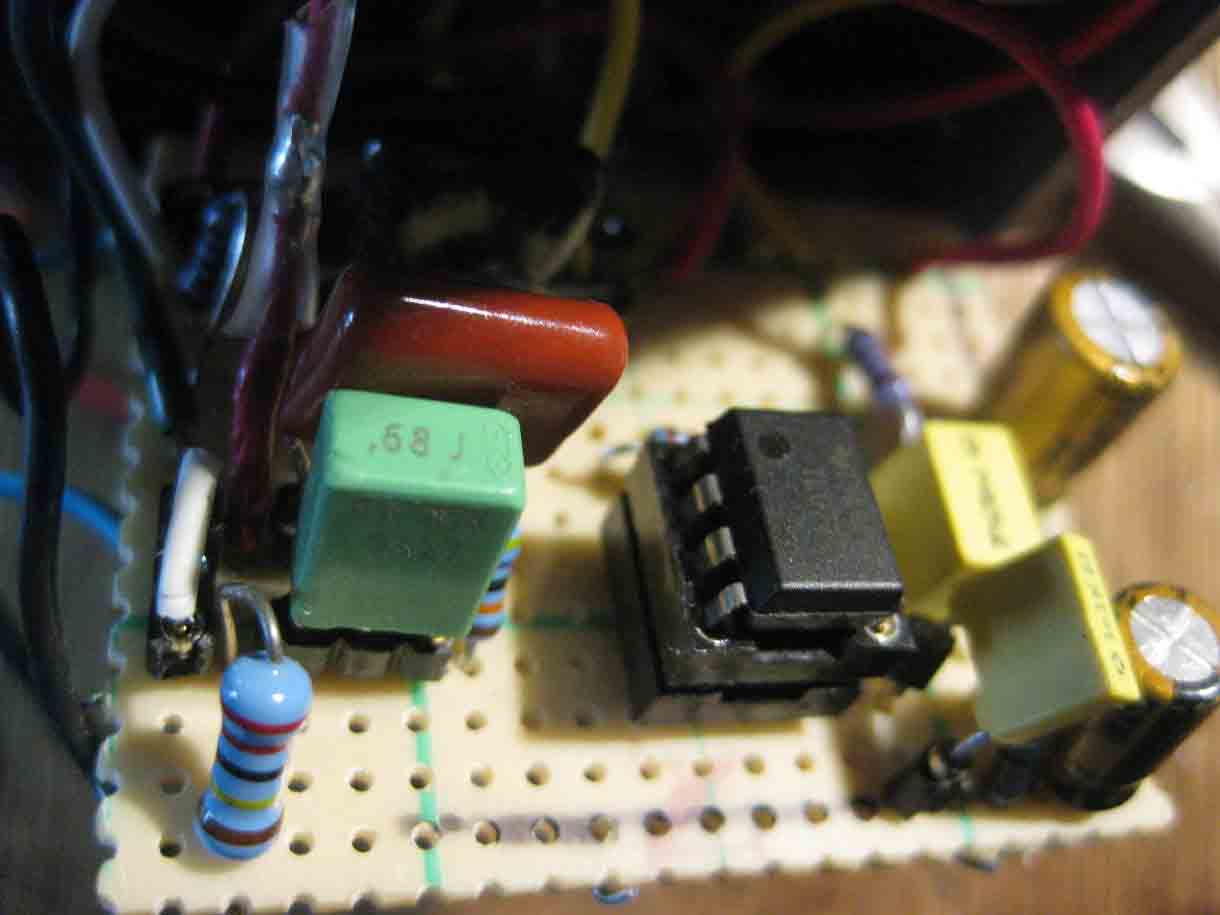
低音がもたつく主な原因?は
入力のカップリングコンデンサーが
0.68uFにしてあったことだと分かった
0.047にすることで解消!
サウンドチェックを繰り返し、
Voiceボリュームにつながるコンデンサーを
0.22から0.1にした
中高域が綺麗に上がってくる
0.68にまで大きくしていたことがあったようで
もっと低音を増やしたいと思っていた様子

なんか勘違いしてたかもなあ
Voiceボリュームを10kBカーブに
Outボリュームを100kAカーブにした
つまりそれは・・
元の回路図
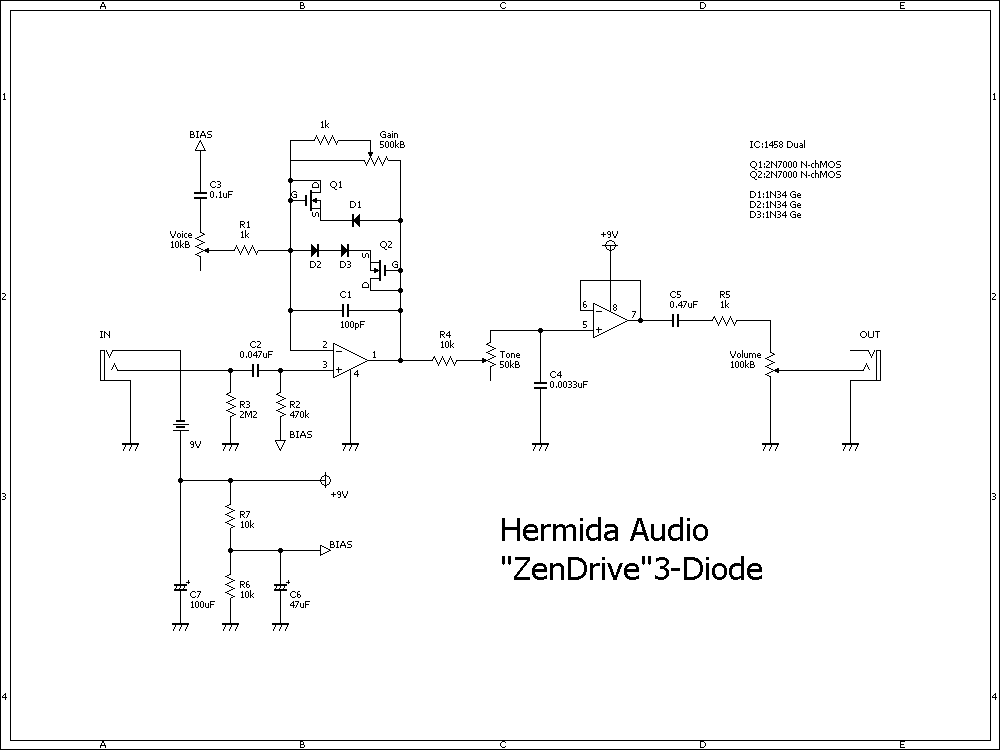
ほとんどオリジナルのZendriveの定数である
(Zendriveも数種類あるらしいが)
低音が多いことと音の太さは違う
特にエレキギターの「歪みモノ」は
いかにうまく低音をカットするか?
が、ポイントになっていると思う

やっと分かったんか

ひえーー
というわけで・・・
Zendriveが復活した
記録と知識として
入力のローカット周波数は7.2Hz
Voiceコントロールは
オペアンプのゲイン段でのローカット定数の可変である
歪みペダルのこの部分低域カットオフ周波数は
720Hzあたりに設定するのがほぼ常識?とされているが
ここでは145Hz~1.6kHzの可変となる
聴感上はミッドの上の方が可変して聞こえる
Toneコントロールとの組み合わせで
いい感じの歪みになる
まだまだ研究の余地があるが
今回はこの辺りで完成としよう
こだわりすぎると、
またラビリンスの沼にはまってしまう
オペアンプを吟味
AD712とTL2262CPで決勝戦をして
ハーフトーンの抜け!を感じて
TL2262CPに決定!
すごくハイファイになって・・・
ロベンフォード氏の音に似ているかもなあ
このエフェクター
中高域が締まった感じというか
他のエフェクターでは得られない感じ?で
独特な音というべきか?
でも、すごく自然とも言える
不思議

ふふふ
Zendrive復活の巻
最後までありがとうございました